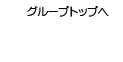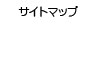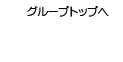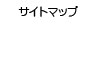|
|
|
| |
| 由来と歴史 |
「川を渡る梵天」は、大仙市花館地区の雄物川対岸、標高210Mの地点にある伊豆山神社〔鎮座は坂上田村麻呂の「東夷征伐」の頃(約1200年前)と伝えられている。〕へ梵天を奉納する伝統的な行事です。
約150年前の江戸時代後期(嘉永年代)、花館村の肝煎りであった齋藤勘左衛門氏によって、五穀豊穣祈願として、また、幕末の若者に活気を取り戻させるためとして始められたと伝えられています。
以来、毎年2月17日(平成17年からは2月11日に変更)に催され今日に至っております。
今では「北国、早春の風物詩」として全国的に紹介され、県内外から観光客が多く訪れるようになってきております。
こちらのページでは「川を渡る梵天」と丸茂グループとの様々な関わりを、また、次の
ページでは今年の「川を渡る梵天」の奉納の様子をご紹介します。
なお、右の地図には、関係箇所の位置が図示されております。 |
|
|
大きな地図で見る | |
|
河床整備 (1月30日) |
|
|
梵天と担ぎ手のみなさんを無事に対岸まで渡すには、安全な河床を準備しておかなければなりません。
伊豆山神社の御祭神、積羽八重言代主神(ツミハヤエ
コトシロヌシ
ノカミ)ら13神のご加護なのでしょう、
青空の下で作業をすることができました。 (−10℃の世界、霧氷が北国の早朝を演出) |
|
|
|
|
待機場所整備(1月30日) |
|
|
「川を渡る梵天」には、地元民や参加者はもとより、県内外からの観光客も数多く訪れます。
お祭りを無事に執り行うには、待機場の整備も欠かせません。 |
|
|
|
|
ロープ張り (2月3日) |
|
|
渡船は川の流れの上にピンと張らせたロープと船外機を使って、梵天と担ぎ手のみなさんを対岸に送り
届けます。 |
|
|
|
|
渡船準備 (2月3日) |
|
|
梵天と担ぎ手のみなさんが乗り込む渡船には、細心の注意のもと平底川船を2艘連結したものが充てられます。
後日、小型船舶協会の検査があります。 これに合格することが不可欠です。 |
|
|
|
|
桟橋設置 (2月5日) |
|
|
乗降時の安全性を一番に考え、念入りに設置されます。 |
|
|
|
|